『ワンパンマン』は、第1期でアニメファンを驚かせた神作画・圧倒的演出によって世界的評価を得ました。
しかし、第2期以降では「ひどい」「作画崩壊」と批判される場面もあり、シリーズ全体の印象に差が出ています。
本記事では、なぜこうした評価が生まれたのか、制作背景・ファンの反応・実際のクオリティ変化を時系列で整理します。
この記事を読むとわかること
- 『ワンパンマン』第2期が「ひどい」と言われた真の理由!
- 制作会社変更による作画・演出の違いと影響!
- ファンの評価が分かれた原因と肯定派の視点!
作画崩壊と呼ばれた背景とは?
『ワンパンマン』第1期は、2015年にマッドハウスが制作を担当し、アニメ史に残るほどの“神作画”で絶賛されました。
一方で、第2期(2019年放送)では制作会社がJ.C.STAFFに変わり、「作画がひどい」「迫力が落ちた」との批判が急増しました。
この章では、なぜ“作画崩壊”と呼ばれるまでに印象が変化したのか、その根本的な理由を整理していきます。
Q:なぜ『ワンパンマン』アニメが「ひどい」と言われたのか?

Q:第2期で何が起きて「作画崩壊」と言われるようになったの?
第1期の完成度が非常に高かったため、第2期のわずかな演出変更や作画クオリティの揺らぎが強く目立ちました。
特に戦闘シーンのカメラワークやエフェクト演出が簡略化され、動きの少なさや“止め絵”が多くなったことが不満の原因とされています。
視聴者の中には「ひどい」というよりも“落差が大きかった”と感じた層が多いのです。
| 要素 | 第1期 | 第2期 |
|---|---|---|
| 制作会社 | マッドハウス | J.C.STAFF |
| 作画の特徴 | ダイナミックな動きと迫力あるバトル演出 | 動きが控えめで、カット数が減少 |
| 演出の方向性 | アクション重視・勢い重視 | 物語重視・会話中心のテンポ |
このように、アニメの方向性自体が変化したことが「作画崩壊」という誤解を生みました。
実際には絵のクオリティが著しく下がったわけではなく、“演出方針の違い”が原因で印象が大きく変わったのです。
第1期と第2期の制作体制・演出方針の違い

Q:制作体制の違いは、どんな影響を与えたの?
第1期を手がけたマッドハウスは、アクションアニメのトップクラスの実力を持つスタジオで、一枚一枚の原画に緻密な動きをつける手法で高評価を得ていました。
一方、第2期のJ.C.STAFFは日常系やラブコメ系の得意なスタジオであり、動的なアクション作画には限界がありました。
さらに、制作スケジュールの短縮や予算の制約が重なり、第1期と同水準の映像表現を再現できなかったとされています。
- マッドハウス:作画監督・原画チームにアクション専門の精鋭を起用
- J.C.STAFF:作業ラインが多く、各話ごとのばらつきが発生
- 制作期間:第2期は1期の約70%のスケジュールで進行
その結果、第2期では「静的な場面構成」が増え、1期にあった勢いと熱量がやや薄まった印象になりました。
ただし、J.C.STAFF版には物語性やキャラクター描写の深みが増しており、決して“失敗作”とは言えません。
視聴者の評価が割れたのは、演出重視か物語重視かという価値観の違いが大きな要因なのです。
ファンが指摘した問題点:作画・テンポ・演出の変化
『ワンパンマン』第2期では、視聴者やファンの間で「作画が雑になった」「テンポが悪くなった」といった意見が多く見られました。
これらの批判は一部のシーンに集中しており、特に第1期で評価された“疾走感ある演出”とのギャップが原因となっています。
ここでは、ファンが具体的にどのような点を問題視していたのかを整理しながら、その背景を分析します。
Q:どんなシーンで「作画崩壊」と言われた?

Q:視聴者はどんな場面で「ひどい」と感じたの?
ファンの不満は、特定の回やシーンに集中していました。特に戦闘シーンの動きが少ない・迫力不足といった声が目立ちました。
また、第2期ではカメラの切り替えが少なく、戦闘の緊張感が薄れたという指摘もあります。
ファンの間で「作画崩壊」と呼ばれた主要エピソードを以下にまとめます。
| 話数 | 主な問題点 | 視聴者の反応 |
|---|---|---|
| 第2期 第3話 | ガロウ初登場の戦闘が静的。スピード感に欠ける。 | 「止め絵が多くて緊張感がない」との声。 |
| 第2期 第7話 | 怪人協会襲撃シーンで背景が単調。 | 「迫力が薄く、群衆戦のスケール感がない」。 |
| 第2期 最終話 | クライマックスの演出が淡白。 | 「第1期のような爆発的な演出がない」と失望感。 |
これらの回では、視覚的な迫力よりも物語進行を優先していたため、アクションを期待していたファンには“落差”が強く映りました。
とはいえ、作画の質が常に低かったわけではなく、静止画中心の演出に偏ったことが誤解を生み出したとも言えます。
戦闘演出の弱体化とキャラ作画の不安定さ

Q:戦闘演出やキャラクターの見せ方はどう変わったの?
第2期では、アクションの「勢い」よりもストーリー展開を重視する構成が取られました。
このため、サイタマやガロウといった主要キャラの表情や動作のディテールがカットされる場面が見られます。
アニメーションの滑らかさよりも、構図や演出の意図を優先した結果、テンポが不自然に感じられたのです。
- カットの省略で“動く作画”よりも“会話演出”が増加。
- キャラ表情の作画監督が話数ごとに異なり、統一感に欠けた。
- 戦闘時のスピード感・爆発描写が減少。
特に、ガロウとサイタマの戦闘では、原作での迫力が再現されず「動かない戦い」と批判されました。
一方で、J.C.STAFFによる心理描写・カメラの固定構図は高く評価される場面もあります。
つまり、ファンの間で評価が割れたのは、「アクション重視派」と「物語重視派」の視点の違いが大きかったのです。
制作会社の変更が与えた影響
『ワンパンマン』第1期と第2期の最大の違いは、制作会社が変わったことです。
この変更は作品の方向性や作画クオリティ、さらにはファンの印象にまで大きな影響を与えました。
ここでは、マッドハウスからJ.C.STAFFへの制作移行がどのような変化をもたらしたのか、その実情を具体的に見ていきます。
Q:マッドハウスからJ.C.STAFFへの移行で何が変わった?

Q:制作会社が変わると、どんな部分が影響を受けたの?
第1期の制作を担当したマッドハウスは、アクション作画に定評のある老舗スタジオです。
一方で第2期のJ.C.STAFFは、学園・日常作品に強い傾向を持つスタジオで、アクション重視の制作体制とは異なる特性を持っていました。
そのため、同じ作品であっても「動き」「演出」「光の表現」が明確に変化しました。
| 制作項目 | 第1期(マッドハウス) | 第2期(J.C.STAFF) |
|---|---|---|
| 演出スタイル | 動きとスピードを重視。戦闘シーン中心の構成。 | セリフ・心理描写を重視。静的構図が増加。 |
| 作画チーム | トップレベルのアクション作画監督陣が参加。 | 外注比率が高く、統一感にばらつきあり。 |
| 映像クオリティ | エフェクト演出・動線・遠近感すべてが高水準。 | 作画安定性を重視。派手さは控えめ。 |
つまり、マッドハウスは「動で魅せる映像」、J.C.STAFFは「静で語る演出」に特化しており、その違いがファンの間で“劣化”と誤解されました。
しかし実際には、制作方針の違いであって、作品の質自体が落ちたわけではありません。
スタッフ構成・スケジュール・予算面の変化

Q:制作体制の内部的な違いも影響していたの?
第2期では、制作期間の短縮や予算の調整により、各話ごとのクオリティコントロールが難しくなったといわれています。
第1期の時点では、原画や作監をリッチに配置する“贅沢な制作環境”が整っていましたが、第2期ではスケジュールの圧迫により、演出のブラッシュアップ時間が不足していました。
- 制作スケジュール:第1期=約1年半/第2期=約10ヶ月
- 作画スタッフ:第2期は外注比率が約40%増加
- 放送前納期:1期は余裕あり、2期は放送直前まで調整
これにより、演出カットの一部で作画の“荒さ”が目立つ回も出ましたが、全体的なストーリーラインはしっかり維持されていました。
むしろ、第2期ではガロウ編などの心理要素を丁寧に描き、映像演出よりも内容を重視する方向性に舵を切っています。
そのため、ファンの評価は「第1期=映像の衝撃」「第2期=物語の深化」と分かれる結果となりました。
ファンの反応と評価の分かれ方
『ワンパンマン』第2期は、放送直後からSNSやレビューサイトで賛否両論が巻き起こりました。
「作画が崩れた」「演出が地味になった」との批判が多い一方で、「ストーリー性が深まった」「ガロウ編が丁寧だった」と肯定的な意見も目立ちました。
ここでは、ファンのリアルな声を中心に、評価がどのように分かれたのかを整理します。
Q:SNS・掲示板での主な意見は?

Q:実際、ファンたちはどんな反応を示していたの?
TwitterやRedditなどのコミュニティでは、第1期と第2期を比較する投稿が多数見られました。
否定的な意見としては「動きが少ない」「迫力がない」という声が多く、一部では「これ本当にワンパンマン?」という厳しい指摘も。
一方で、ストーリー重視派のファンは「ガロウの人間性が丁寧に描かれていて良い」と好意的に受け止めています。
| 評価タイプ | 主なコメント傾向 | 特徴 |
|---|---|---|
| 否定派 | 「1期の動きが神だったのに」「第2期は静止画ばかり」 | アクション・作画クオリティ重視のファン層。 |
| 肯定派 | 「心理描写が深まった」「ガロウの葛藤が伝わる」 | 物語・テーマ性重視のファン層。 |
| 中立派 | 「第1期とは違う方向性。これはこれであり」 | 制作方針の違いとして受け入れるバランス層。 |
このように、ファンの評価は明確に分かれており、「第1期が基準」となったことで、第2期の印象が厳しく見られた側面があります。
しかし同時に、シリーズ全体としての物語の深みが増したことを評価する声も根強く存在しました。
批判だけじゃない?肯定派が評価したポイント

Q:批判が多い中で、どんな点が評価されていたの?
否定的な声の裏で、「第2期だからこそ良かった」と語るファンも多くいました。
特に評価されたのは、ガロウの人間的な成長や、サイタマの日常描写の増加です。
第2期では戦闘中心ではなく、ヒーロー社会の歪みや人間ドラマに焦点を当てた構成となっており、これは漫画ファンから高く評価されています。
- ガロウの葛藤や孤独を丁寧に描写。
- サイタマの「強さの虚しさ」に共感する演出。
- 日常パートの増加でギャグとシリアスのバランスが向上。
さらに、作画面でも一部話数では高い完成度を保っており、特定回(例:第2期第9話「ガロウVSタンクトップマスター」)は“作画神回”として話題になりました。
このように、第2期の評価は単なる「作画崩壊」ではなく、演出方針の変化をどう受け止めるかで印象が大きく分かれていたのです。
第2期以降でも観る価値はある?
「作画がひどい」と言われた『ワンパンマン』第2期ですが、それでも多くのファンが視聴を続けています。
実際、映像面に不満を感じる部分があっても、物語やキャラクターの魅力がしっかり維持されている点は見逃せません。
この章では、第2期以降にも存在する“観る価値”を明確にし、ファンがなぜ作品を支持し続けているのかを探ります。
Q:作画が悪くても楽しめる要素とは?

Q:「作画崩壊」と言われても面白い理由ってあるの?
『ワンパンマン』は単なるアクションアニメではなく、“ヒーローとは何か”という哲学的テーマを持っています。
そのため、戦闘の迫力が多少落ちても、物語の本質が損なわれることはありません。
むしろ第2期以降では、登場人物たちの人間ドラマが深く描かれており、作品全体の厚みが増しています。
- サイタマの「強さの孤独」と内面的な葛藤が明確化。
- ガロウの視点から見る“悪の正義”が深掘り。
- ヒーロー協会の腐敗や社会風刺が強調されている。
こうしたテーマ性の深さは、映像の派手さに頼らない新たな『ワンパンマン』の魅力です。
つまり、第2期以降は「アクション作品」から「群像劇」へと進化したと言えるでしょう。
演出以外の魅力:物語性・キャラ・音楽面の評価

Q:アニメの“演出以外”で評価できるポイントは?
第2期の注目点は、音楽・演技・脚本の完成度にあります。
特にBGMやオープニングテーマはシリーズ全体のテンションを引き上げており、声優陣の演技も安定しています。
アクションが控えめな分、セリフや間の取り方でキャラクターの感情を巧みに表現しています。
| 要素 | 評価ポイント | 代表的な魅力 |
|---|---|---|
| 音楽 | オープニング「静寂のアーケード」が高評価。 | 疾走感のある楽曲で緊張感を演出。 |
| 声優 | サイタマ役・古川慎、ガロウ役・緑川光の演技。 | 静と動を巧みに表現し、作品に厚みを与える。 |
| 脚本 | 心理描写・社会批判が強化された構成。 | 物語のメッセージ性が際立つ。 |
これらの要素が、第2期の「作画以外の強み」としてファンに評価されています。
特にガロウ編では、ヒーローと怪人の境界を描いた哲学的ストーリーが高く支持されました。
- アニメとしての完成度は下がっても、物語の核はより濃密に。
- 心理描写と演技力の向上により、作品世界に深みが増す。
- 映像ではなく“心情で魅せる”新しい方向性の確立。
このように、『ワンパンマン』第2期以降も観る価値は十分に存在します。
映像美を求めるか、物語性を味わうか──その選択次第で、本作の印象は大きく変わるのです。
まとめ:『ワンパンマン』アニメと作画論争の本質
『ワンパンマン』アニメの“作画崩壊”という評価は、単なる品質の問題ではなく、ファンの期待と制作方針のズレによって生まれたものです。
第1期が世界的に称賛されたことで、視聴者のハードルが極端に上がり、第2期の「演出重視」スタイルが“劣化”と受け止められました。
しかし、その裏には制作体制の変化やテーマの深化といった、より複雑な要因が存在しています。
Q:結局、『ワンパンマン』アニメは“ひどい”のか?

Q:最終的に、『ワンパンマン』アニメは「ひどい」と言えるの?
結論として、“ひどい”とは言い切れません。
第2期以降も作品としての完成度は高く、物語・キャラ描写・音楽演出のレベルは安定しています。
むしろ、アニメとしての方向性が「勢い」から「深み」へとシフトしただけであり、視聴者の求めるスタイル次第で評価が変わる作品です。
| 評価軸 | 第1期 | 第2期以降 |
|---|---|---|
| 映像表現 | 圧倒的作画とスピード感。アクション重視。 | 静的演出で心理描写を強調。物語重視。 |
| テーマ性 | “強さの孤独”を象徴的に描く。 | “正義と悪の曖昧さ”を掘り下げる。 |
| 印象 | 一撃の爽快感。 | 余韻の残る深さ。 |
このように、『ワンパンマン』のアニメは“違う良さ”を持っているに過ぎません。
作画だけを切り取れば物足りなく感じるかもしれませんが、テーマ性と演出の変化を理解すれば、むしろ新しい一面が見えてきます。
ファンが再評価すべき『ワンパンマン』の本質

Q:今後、『ワンパンマン』をどう楽しむべき?
これから『ワンパンマン』を観る人に伝えたいのは、“作画”ではなく“内容”に注目してほしいという点です。
第2期以降では、サイタマとガロウという対照的な存在を通して、ヒーロー観の本質がより丁寧に描かれています。
つまり、『ワンパンマン』は単なるバトルアニメではなく、「強さ」「正義」「社会」の意味を問う哲学的作品へと進化しているのです。
- 映像の派手さではなく、物語の深さに価値を見いだす。
- 作画の変化は“衰え”ではなく“表現の転換”。
- ファンの期待値が高いほど、次のシーズンに希望が持てる。
『ワンパンマン』の魅力は、時代や制作環境が変わっても失われません。
むしろ、変化を受け入れることで、作品をより多面的に楽しめるようになるのです。
その意味で、“ひどい”という言葉はもはや通用しません。『ワンパンマン』は今も進化を続けているのです。
この記事のまとめ
- 『ワンパンマン』第2期は制作会社の変更により演出方針が大きく変化!
- 「作画崩壊」と言われた背景には、マッドハウスとJ.C.STAFFの表現スタイルの違いがある。
- ファンの評価は「アクション重視派」と「物語重視派」で二極化。
- 第2期では心理描写・テーマ性が深化し、“群像劇”としての魅力が強化。
- 映像の派手さよりも、キャラクターの心情や社会的テーマに注目すべき!
- 『ワンパンマン』は「ひどい」ではなく、「進化した」作品として再評価されている。

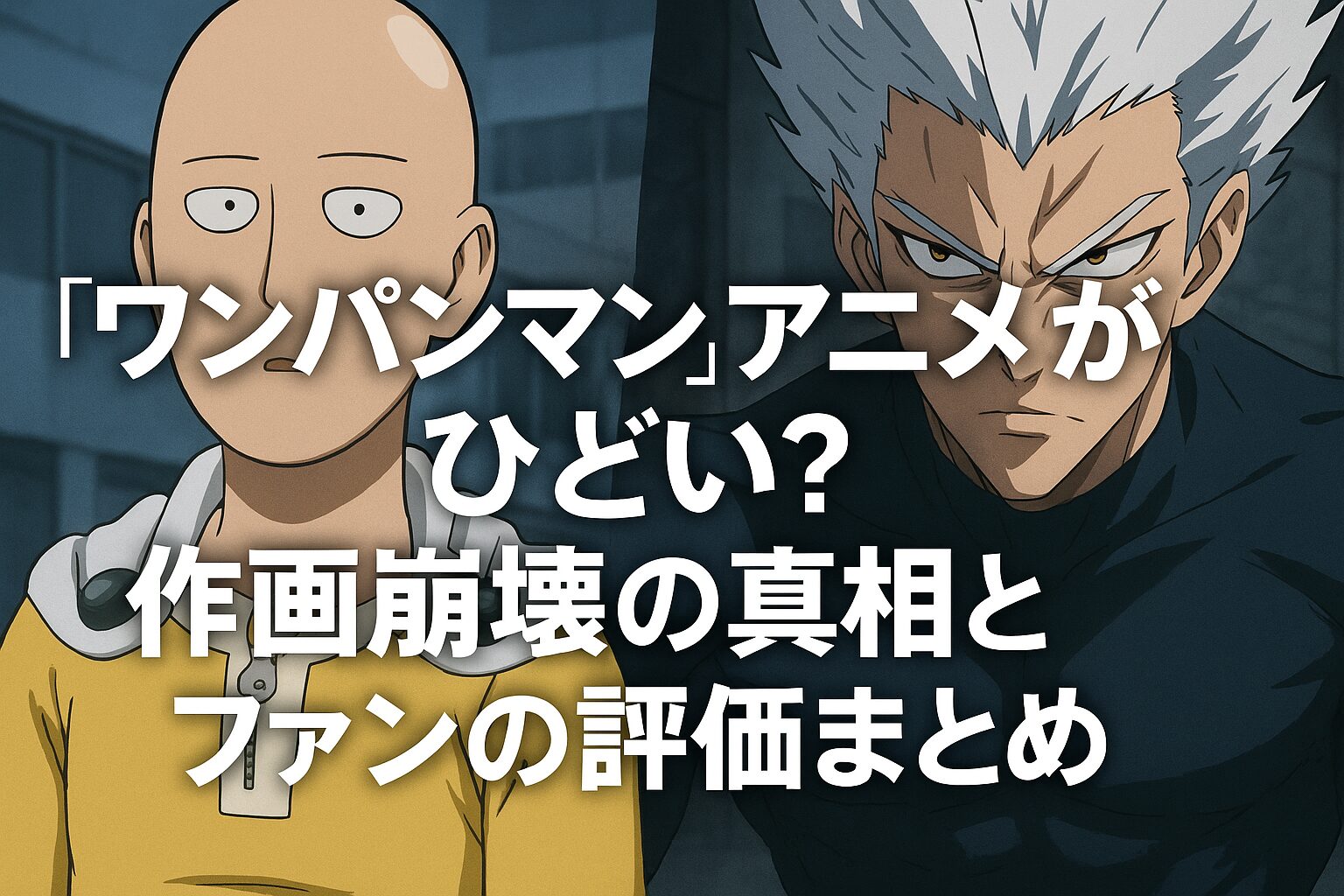
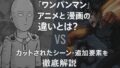
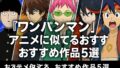
コメント