「編集者って、よく見たら鬼だったり優しかったりしますよね…」「ざつ旅」では、ちかの最初の担当・吉本翔子さんが“旅に出なさい”と押してくれる、編集者らしからぬ優しさが印象的です。
必要なのは、ただイエスを言ってくれる人ではなく、心を動かすひとこと。この記事では、吉本さんがちかに注いだ編集者としての矜持と、人間としての導きの意味を深掘りします。
この記事を読むとわかること
- 吉本翔子の「旅に出なさい」という言葉の本当の意味
- ちかが旅を通して再び“描きたい”と感じるようになった理由
- 編集者と作家という枠を越えたふたりの信頼関係のかたち
吉本翔子は“背中を押す編集者”?その言葉の本質を探る
「旅に出なさい」──ただの提案じゃなかった?
物語の冒頭、ちかが連載打ち切りに落ち込み、何も描けなくなっていたとき、吉本翔子が口にした「旅に出なさい」という言葉は、単なる気休めや提案には思えません。
むしろそれは、「描けないなら、まずは動け」という一種のスイッチだったのです。このセリフが突き刺さるのは、彼女がちかの内面をよく理解しているからにほかなりません。
普通の編集者なら、「もう少し頑張ってみよう」や「しばらく休んだら?」といった曖昧な励ましを与えがちですが、吉本さんは違います。
彼女の語彙には曖昧さがない。それでいて強すぎない。どこか“宿題を出す先生”のようでもあります。
実際、吉本さんの語り口はフラットで押しつけがましくなく、命令でも助言でもない「行ってみたら?」という軽やかさに包まれています。
しかし、その一言には、「あなたならきっと何かを見つけられる」という信頼と期待が込められているように感じられます。
この一言が物語を動かす起点になっていることからも、彼女の“導く力”はただの編集業務を超えていると言えるでしょう。
ちかが再び創作と向き合うことになる第一歩は、この“非・命令形”の提案によって始まったのです。
吉本さんが見抜いていた“ちかの限界”と可能性
描けない──それは創作者にとって致命的な状態です。しかし吉本さんは、その表面的な「描けない」に引きずられることなく、ちかの心の奥に潜む“描きたいのに描けない”というもどかしさを見抜いていました。
彼女はあえて問い詰めたりせず、静かにちかの目線の高さで寄り添います。これは“編集者”というよりも、むしろ“共犯者”のような立ち位置です。
「逃げてもいいよ」とは言わず、「このままじゃ終わらないよね?」という目線を送っているように見えます。
しかもその助言は、決して情に訴えるようなものではなく、むしろロジカルな視点でちかの状況を整理しています。
「いま描けないのは才能がないからではなく、単に“場所”が合ってないだけかもよ?」とでも言いたげなニュアンス。
そんな冷静さと情熱のミックスが、ちかの心をじわじわと動かしていきます。一見すると何気ないやりとりですが、吉本さんの言葉には“問いかけ”の形をした魔法のような力があります。
それは押しつけないからこそ、心に残る。彼女の言葉が「刺さらないようで刺さる」のは、まさにそうした緻密な距離感の賜物です。
心を見透かされるようで、ちょっとこわい?
ちかが「旅に出る」ことを決めたあとも、どこか吉本さんの視線を意識しているように感じられます。それは干渉や圧力ではなく、
「もう言い訳できないな……」という静かな覚悟の表れかもしれません。自分でも気づかない“創作への渇望”を見抜かれたような、そんな不思議な感覚です。
特に印象的なのは、ちかが旅先で「描きたい」とふいに思う瞬間。そのとき、吉本さんの言葉がふとよぎる場面には、「あれってやっぱり的確だったんだな」と感心させられます。
創作における“根っこ”を言い当てられるというのは、嬉しさと同時に、ちょっと怖い体験でもあります。
しかし、その怖さは決して否定的なものではありません。「自分は本当は描きたいんだ」という気づきをくれる存在に、恐れと同時に感謝を抱いてしまう。
そういった感情の交錯が、ちかと吉本の関係には漂っています。
だからこそ、このふたりのやりとりは“指示と従属”ではなく“気づきと自立”の関係として描かれているのです。
旅に出るという決断も、創作への再チャレンジも、ちか自身の意志で行われているように見えて、実は吉本さんという“心のナビ”の存在があってこそなのかもしれません。
ちかの“迷い”と“やる気”が交差する瞬間
「言われた通りにしてみた」──その1歩が全てを変えた
ちかが「旅に出なさい」という吉本編集者の言葉を素直に受け入れた瞬間、それは単なる“従順な主人公”ムーブではありませんでした。一見すると「言われた通りにしてみた」という軽いノリ。
しかしその実、彼女の中では「描けない自分」に対する密かな反発や、もしかすると小さな賭けのような気持ちが交錯していたのです。
この行動は、「ネタを集めるための旅」などという実利的な発想とは一線を画しています。むしろ、ちかにとっては“動くことで何かが変わるかもしれない”という、
理屈を超えた試行錯誤だったのでしょう。つまり、やる気の表面張力がぎりぎりで保たれている中での一滴が、この旅という行動だったのです。
重要なのは、「やる気がない」わけではなかったという点。ちかはやる気を“出せない”だけだったのです。
あまりにも描けない自分に対して、心のどこかで「何を描いても価値がない」というフィルターがかかっていた。
つまり、才能の欠如ではなく、セルフイメージのバグ。旅は、それをリセットする強制再起動のようなものでした。
結果的に、この“ちょっとノッてみた”が、彼女の創作における再出発となったのです。だからこそ、この1歩は、漫画的には地味でも、ちかの物語の中では極めて重大な転機となったのでした。
旅先で生まれた、“描きたい”という感情
旅の最中、ちかの中にふいに湧き上がった感情──「描きたい」。それは、締切に追われていたときの“描かねばならない”とは明らかに異なるものでした。
風景や人々の表情、空気感のようなものが、言葉よりも先に心を満たしていき、気がつけば手が動いていた。これはもはや創作衝動というより、「ここを誰かに伝えたい」という本能的な行為です。
ちかは旅先で、誰かの評価を得るためではなく、「いま、この瞬間を残したい」という気持ちでペンを握ります。これは創作者にとって極めて純度の高い動機です。
創作が「労働」から「遊び」へと変わる瞬間でもありました。
実は、創作意欲というのは、モチベーションがあるときだけ発動するものではありません。むしろ、ふとした風景の中や、想定外の体験の中で自然と浮上するものです。
ちかの場合、まさにそれが「旅」という非日常によって引き出されたわけで、「評価されたい」や「うまく描きたい」という意識すら横に置いて、ただ「描きたい」が主役になったのです。
この“無欲の創作”こそが、ちかにとって本来の創作の喜びを思い出させる鍵となりました。仕事にしすぎると見失いがちな、“はじめて漫画を描いたときのわくわく”が、旅の中で自然と蘇ったとも言えるでしょう。
描けるようになった“心のしくみ”とは?
では、なぜちかは再び描けるようになったのでしょうか。そこには明確な“心のしくみ”の変化があります。まず一つは、「描けないこと=悪いこと」という思い込みが、旅によって一度リセットされたこと。
描かなくても何も責められない環境の中で、「じゃあ描いてみようかな」と自然に思える心理的余白が生まれたのです。
このとき、ちかの思考は「また失敗するかも」ではなく、「描いてみてから考えよう」に切り替わっていました。この思考の変化こそ、創作再開のカギです。
行動の前に完璧さを求めなくなったことで、彼女の中にあった“心のブレーキ”が外れたわけです。
また、旅の中で感じた“感動”や“もどかしさ”が、自然とアウトプットへの欲求に変換されていった点も見逃せません。
人は自分の内面に湧いた気持ちを外に出したくなる生き物であり、それは漫画家であるちかにとっては「描くこと」に直結するのです。
最終的に彼女は、自分が本当に欲しかったのは「描くことにOKを出してくれる自分」だったと気づきます。描けるようになったのは、技術でも時間でもなく、
“自分で自分に許可を出せたから”だったのです。この内面の回復が、ちかの創作人生におけるリスタートとなりました。
ふたりの関係にある“上下”ではなく“横のつながり”
ちかが見せた“ちょっと照れた感謝”
ちかが見せる吉本への態度には、微妙な「好き・嫌い」や「信頼・不信」が交錯していますが、ある場面では明らかに「この人、嫌いじゃない」と言わんばかりの“ちょっと照れた感謝”が垣間見えます。
言葉にはせず、態度でも全面的には出さない――けれど、ふとした視線や間合い、あるいは旅の途中の小さなリアクションに、そうした気持ちはにじみ出るものです。
ちかにとって吉本は、最初は「上司」的な立ち位置であり、若干の警戒心すらあったはずです。にもかかわらず、旅を重ねるうちにその関係性は微妙に変化していきます。
特に、ちかがスケッチブックを再び開いたとき、そこには明らかに吉本への感謝のような感情が含まれていました。
ちかが再び描き始めたその行為自体が、実は「ありがとう」の非言語的表現なのです。吉本が強制することもなく、期待を押しつけるでもなく、
ただ横で同じ景色を見ているだけで、ちかの中に何かが芽生えた。これは、単なる“仕事相手”という関係を超えた、心の揺らぎによって生まれた「横のつながり」の証でもあります。
編集者と漫画家という「上下」の構造が前提にある業界において、このふたりの距離感は珍しく、“対等”に近い。むしろ、ちか自身がその対等さに無意識的に救われているのではないでしょうか。
吉本さんの“突き放さない距離感”が心地よい理由
吉本という人物は、ちかに対して「何を描け」「こうしろ」と直接的に指示することはありません。かといって完全に放任するわけでもなく、
必要な場面ではぽつりとヒントのような言葉を投げかけてきます。これは絶妙なバランスで、距離を取りつつも常に“見ている”という姿勢が保たれているのです。
吉本が見ているのは、“すでに描ける人”ではなく、“描こうとしている人”。これは彼の編集方針というより、人間観察の結果かもしれません。
まだ形にならない可能性を、種の段階で見つける力。それこそが編集者・吉本の強みであり、ちかのような不安定な才能に寄り添うスタイルなのです。
干渉しすぎず、放置もしない。その曖昧さがちかにとっては息苦しくなく、むしろ自発性を促す安全な距離として作用しています。
常に後ろにいるわけではないが、必要なときには“そこにいる”という感覚。まるでGPSに頼らずとも「なんとなく安心できる同行者」がそばにいるような、そんな関係性です。
結果的に、ちかは「見張られている」わけでも「放任されている」わけでもない、適度な自由と安心の中で描く喜びを取り戻すことができたのです。
編集者と作家を超えた“旅の仲間”として
この作品の面白いところは、編集者と作家というビジネスライクな関係が、次第に“旅の仲間”へと変容していく点です。
吉本はガイドではなく、あくまで「同行者」としてのポジションを貫いています。彼自身も旅を楽しんでいる様子があり、ちかと対等な立場で同じ風景を眺めているのが印象的です。
旅という非日常の空間で、人は肩書きを一時的に外すことができます。そこで生まれるのは、「上司と部下」ではなく「人と人」としての関係性。
吉本とちかのやり取りは、そうした人間的な交流を象徴しており、名刺の肩書きではなく、感性でつながる関係が描かれているのです。
吉本の最大の功績は、「描くって楽しい」という感覚をちかに思い出させたことかもしれません。
それはテクニックや助言ではなく、「隣にいる誰かの存在」から自然ににじみ出るものであり、いわば“他者を通じて自分を取り戻す”という現象です。
もはやふたりは、創作という同じ川を漕ぐカヌーのペアのような存在。目的地は定まっていなくても、「一緒に進んでいる」という感覚がちかの心を支えているのです。
まとめ:ふたりの関係にある“上下”ではなく“横のつながり”
ちかは言葉にしなくても、吉本への感謝を態度で見せるようになります。吉本は指示も干渉もしない絶妙な距離感で、ちかの創作意欲をそっと支えました。
編集者と作家という関係に縛られず、“旅の仲間”として同じ風景を見ているふたり。この「横並び」の関係性が、ちかの「描きたい」という気持ちを引き出します。
吉本の存在は、「描けるかどうか」ではなく「描こうとすること」を見守る安心感そのもの。ふたりの旅は、肩書きを越えた信頼と共鳴の物語でもあるのです。
そしてその関係性が、ちか自身の「再起の物語」に静かに火を灯していきます。
この記事のまとめ
- 吉本翔子の助言は、ちかの創作意欲を引き出す“鍵”だった
- ちかの旅は、逃避ではなく再出発へのステップだった
- ふたりの関係は、上下ではなく“横並び”の信頼関係である
- 「描きたい」という気持ちは旅の中で自然と芽生えていた
- 干渉しない寄り添い方が、ちかの心に火を灯した


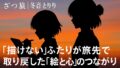
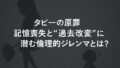
コメント