「ちょっと旅に出たい…」と勢いで決めた行き先、SNSに投げたらまさかの人気投票に?
そんな“ざつな旅”に、漫画家志望のちかとアウトドア一筋のハッスーが一緒に飛び込んだらどうなるか、気になりませんか?
この記事では、常識を超えた親友の存在がちかの創作と心をどう動かしたのか、その“裏側”にも迫ります。
この記事を読むとわかること
- ちかの“ざつ旅”がどのように始まったのか、そのきっかけと背景
- 親友ハッスーの言葉や存在がちかに与えた心理的な影響
- 旅を通してちかが創作面・内面でどう変化していったのかの過程
“ざつ旅”はこうして始まった──ちかの衝動とハッスーの一言
「漫画のネタにしたい」ちかの思いつきがすべての始まり
漫画家志望の女子大生・鈴ヶ森ちかが旅に出るきっかけは、いささか衝動的なものでした。「漫画のネタにしたい」という気まぐれから、SNSで行き先のアンケートを募集したのです。
フォロワーからすれば、ちょっとした遊び感覚だったかもしれません。ところがその“雑な思いつき”が、後に彼女自身をじわじわと変えていく旅になるのですから、人生何が起きるかわかりません。
ちかの投稿はたちまち注目を集め、多くの反応が寄せられました。リプライ欄は盛り上がり、見知らぬ人々が投票し、行き先を決めていく。普通なら、ここで「やっぱりやめた」となるところですが、ちかはその勢いに乗ってしまいます。
もしかしたら、それは“逃げ”だったのかもしれません。将来や夢に対する不安、自分の創作に対する自信のなさ。そういったモヤモヤから目をそらすための、遠回りな選択肢だったのです。
ただ、彼女の選んだ“ざつ旅”というスタイルは、予定調和を拒むぶん、自分の内面と否応なく向き合う時間をくれるものでした。そう、最初はネタ探し。けれど、それが自分自身を知る旅にもなっていったのです。
「行ってみる?」ハッスーの軽さが旅を動かす
SNS投票で行き先が決まったとはいえ、ひとりで旅に出るのはなかなかハードルが高いものです。そんなとき、あっさり「行ってみる?」と一緒に付き合ってくれたのが、高校時代の親友・蓮沼暦、通称ハッスーでした。
大学生活を送りながらもアウトドアを楽しむ彼女は、旅のこととなれば腰が軽いどころか、浮いてるんじゃないかと思うほどのノリのよさを発揮します。
この“軽やかさ”は、ちかにとって救いでもあり、時に圧でもあります。というのも、ちか自身はどちらかといえば慎重派で、想像の中でぐるぐる思考を巡らせてしまうタイプ。それに対し、ハッスーはとにかく「動いてから考える」人間です。
しかし、この真逆なタイプの親友がいるからこそ、ちかは動き出せたのです。「いいじゃん、行ってみようよ」と言われれば、なんだかそれだけで背中が押されてしまう。
読者のみなさんにも、そんな“無責任に見えて、実は超貴重”な友人がいるのではないでしょうか?一見ただのノリでも、そこには信頼と安心感という名の土台があるのです。
“ざつ”の中に宿る、本気の第一歩
一見ふざけているような「ざつ旅」というコンセプト。けれど、ちかにとっては、実は本気の第一歩でした。旅の計画はずさんで、持ち物も適当、時刻表なんて見ない。
そんな行き当たりばったりな移動のなかで、彼女は“進んでいる感覚”を確かに持っていたのです。
それまでのちかは、「何かを始めるには準備が完璧でなければ」と考えがちでした。けれど、ハッスーと一緒に雑に踏み出してみると、不思議なことにどんどん前に進んでいける。
彼女が心の中でつぶやいた「雑だけど、ちゃんと進んでる気がした」という感覚は、多くの創作を志す人にも共通する気づきではないでしょうか。
完璧じゃなくていい。むしろ、予定通りじゃないからこそ見える景色がある。それを体感したちかは、この旅を「ただのネタ集め」では終わらせなかったのです。
“ざつ”という言葉の中に、本当の自分の輪郭が少しずつ浮かび上がっていく。そんなはじまり方も、悪くないと思えてきます。
旅先で見えた、自分の輪郭と“描きたいもの”
心が動く瞬間は、いつも決めてなかった風景から
ちかの“ざつ旅”に共通しているのは、ルートが綿密に決まっていないことです。目的地はSNSの投票で決まり、移動手段や宿泊場所も現地の空気次第という、自由すぎるスタイル。
ところが、そうした“予定外”のなかにこそ、ちかの感情は思いがけず揺さぶられるのです。
たとえば、駅前の雑多な風景、雨に濡れた神社の石段、道端で出会った猫。観光パンフレットには載らないような場面こそが、ちかの心のどこかに静かに入り込んでいきます。
何かが「美しい」と感じられる瞬間に、理由は要らないのかもしれません。それは理屈ではなく、直感で“感じてしまった”もの。描こうとして描けるものではなく、偶然の出会いが呼び起こす感覚です。
創作を志す人にとって、ネタは“探す”ものだと思いがちですが、ちかの旅を見ていると、むしろ“拾う”ものなのではないかと思わされます。
そして、その拾い方はいつも、心のセンサーが勝手に反応してしまう瞬間にあります。つまり、予定通りの旅では拾えないのです。
ちかにとって、この気まぐれな旅は、自分のアンテナが何に反応するのかを知る旅でもありました。きっちり決められたスケジュールの中では、気づけなかったもの。
それが、不規則で不安定な「ざつ旅」だからこそ、拾えたというのはなんとも皮肉であり、創作の妙でもあります。
何気ない会話が、心の奥を揺さぶる
旅先での刺激は風景だけにとどまりません。むしろ、人との何気ない会話の中にこそ、ちかは深く揺さぶられることが多いようです。特に、親友・ハッスーとのやりとりはその典型です。
「それ、なんでそんなに気にしてるの?」「もっと適当でいいんじゃない?」というハッスーの一言に、ちかは何度も立ち止まらされます。
本人に悪気はないし、むしろ励ましのつもり。でも、そういった“予告のない正直”が、ちかの心の奥にある“自分でも見ないふりをしていた感情”に直撃するのです。
たとえば、駅のベンチでぼーっとしていたときの会話。ハッスーが冗談半分に「帰ったらちゃんと漫画描くのかよ」とツッコんだ一言に、ちかは不意に胸がつかえるような気持ちになります。
ハッスーは笑っているのに、自分だけ泣きそうになる。それはきっと、図星だから。
こうした“感情のズレ”が旅の間に何度か訪れます。おもしろいのは、ハッスーはそれをまったく気にせず次の話題に進むということ。
つまり、泣きそうになってるのはちかだけ。けれど、そのズレの中に、ちかは確かに「本音」を見出していきます。
人は、自分の言葉ではうまく説明できない気持ちを、誰かとの会話の中で“思わず”こぼしてしまうときがあります。それが、自分の輪郭を知るための小さなきっかけになるのです。
“描けなかったもの”に触れたとき、変化は始まる
創作を続けていると、「なぜか描けないもの」に出会うことがあります。
構図が浮かばない、感情が言葉にならない、あるいはキャラクターが動いてくれない。ちかも、そんな“描けなさ”に何度も直面していました。
しかし、旅の中でふと立ち寄った場所や、偶然の出会いが、その「描けない理由」を静かに溶かしていくことがあります。
たとえば、海辺の小さな神社で見た風鈴が揺れる光景。それを見たちかは、以前描こうとして諦めたシーンの絵が突然頭に浮かんだのです。
ハッスーが何かを言ったわけでもなく、特別な事件が起きたわけでもない。ただ、“その場”にいたことが意味を持ったのです。
「今の気持ちなら描ける気がする」と感じる、その瞬間。創作において何より大切なのは、たぶんそういう“心で拾った瞬間”なのだと思います。
誰かに言われたからではなく、自分の内側から湧き出たもの。旅は、それを引き出す鏡のような存在です。描けなかったものが描けるようになるとき、それは自分の変化がはじまったサイン。
あなたにも、そんな“ふとした瞬間”があったのではないでしょうか?
親友だからこそ、刺さる言葉がある
「もっと変わっていいんじゃない?」その一言の重み
ハッスーは、飄々としていて、あまり深く考えていないように見えるタイプです。でもその“軽さ”こそが、時としてちかの胸にずしんと響くのです。
たとえば旅の途中、商店街のベンチで休んでいたとき、ちかが何気なく「この旅って意味あるのかな」と漏らした場面。ハッスーはそれに対し、ポテトを頬張りながら「もっと変わっていいんじゃない?」と一言返しました。
本人としては、軽口のつもりだったのでしょう。しかしその言葉に、ちかは反応できませんでした。ただ、少しだけ目を伏せて、何も言わずにアイスコーヒーの氷をかき回していたのです。
「変わっていい」——言葉だけ見れば前向きな提案にも見えますが、それは裏を返せば「今のままでは足りないのでは?」という含みを感じさせる言葉でもあります。
しかもそれを言ったのは、気を許している親友。だからこそ、刺さるのです。
親友だから、遠慮がない。けれど親友だからこそ、その言葉には自分を見抜かれているような“怖さ”もある。
ちかにとって、このひと言は単なる旅の中の一場面ではなく、自分の内面と静かに向き合わざるを得ないきっかけとなりました。
ハッスーは、あれこれ考えて言葉を選ぶタイプではありません。でも、だからこそ本音のように聞こえる。そしてちかは、そんな“軽くて深い言葉”に、少しずつ動かされていくのです。
言葉にならない気持ちを、風景が代弁してくれる
ちかの旅は、常に“何かを言語化したい”という気持ちと共にあります。けれど、気持ちというのは案外、言葉にならないものです。
特に、自分の中でぐるぐる渦巻いている感情や迷いは、口に出すと薄っぺらくなってしまうことすらあります。
そんなとき、風景が代わりに語ってくれることがあります。たとえば、夕暮れの川沿いをハッスーと並んで歩いていたとき。会話はなくても、その沈黙の中に、ちかは何かを感じ取っていました。
風の音、川の流れ、日が傾いていく空。言葉で説明するのは難しいけれど、「ああ、いまの自分はこれでいいのかもしれない」とふと納得できるような感覚があったのです。
その“言葉にならない何か”は、後から振り返るととても大切なもので、創作においては特に重要な感情の種になります。風景や空気が、ちかの心にそっとラベルを貼ってくれたような瞬間だったのでしょう。
□ちかの気持ちの変化ポイント3つ:
以前は「旅=ネタ集め」だったのが、「旅=自分を知る時間」になった
ハッスーの言葉を“刺激”ではなく“支え”として受け取れるようになった
「うまく言えない感情」も作品にしていいと思えるようになった
このように、沈黙の時間や風景は、ちかにとっての“心の翻訳機”だったのです。
「あの旅がなかったら、今の私はいない」
旅の終わり、駅のホームで電車を待っているとき、ちかがふとこぼした一言がありました。「あの旅がなかったら、今の私はいないと思う」。それは独り言のようであり、ハッスーへの感謝のようでもありました。
最初はネタ探しのつもりだった旅。けれど、気づけばそれは、自分の輪郭を確認する時間になっていました。SNSの票に従って始まった“ざつ旅”は、ちかにとってまったく“ざつ”ではなかったのです。
予定通りに進む人生の中では、こうした偶然の出会いや感情の揺れはなかなか起きません。旅は、不確かさを受け入れなければならないもの。
ハッスーという存在がそばにいたことで、その不確かさが“怖い”から“楽しい”に変わっていったのです。
創作の根っこには、こうした「体験」や「感情」が必要です。ちかは、ハッスーと一緒に旅をする中で、「どうすれば上手に描けるか」ではなく、「何を描きたいのか」に気づいていきました。
それは技術的な上達とは別の意味での、大きな成長でした。
だからこそ、旅の終わりにちかは言ったのです。「あの旅がなかったら、今の私はいない」。そして、その“今の私”は、きっと以前よりもずっと“描くこと”に近づいているのです。
まとめ:ちかとハッスーの“ざつ旅”が教えてくれたもの
思いつきから始まった旅は、ちかにとって創作以上の意味を持ち始めました。
ハッスーの何気ない言葉や行動が、ちかの迷いをほぐし、前に進む勇気をくれます。
予定外の風景や沈黙の時間が、自分の本音と向き合わせてくれるのです。
描けなかったものが描けるようになる瞬間には、心の変化がそっと宿っていました。
親友の存在が、ちかの旅と人生を豊かにしたのは言うまでもありません。
“ざつ”に見えた旅は、実はちかの中でいちばん丁寧に積み重ねられていたのです。
だからこそ、あの旅がなかったら、今の彼女はきっといないのでしょう。
この記事のまとめ
- ちかの旅はSNSの一言から始まった
- ハッスーの言葉がちかの背中を押した
- 予定外の出会いが創作の刺激になった
- 沈黙や風景が心の変化を導いた
- 親友の存在が人生と創作に深く影響した
- “ざつ旅”は、ちかにとって一番丁寧な旅だった

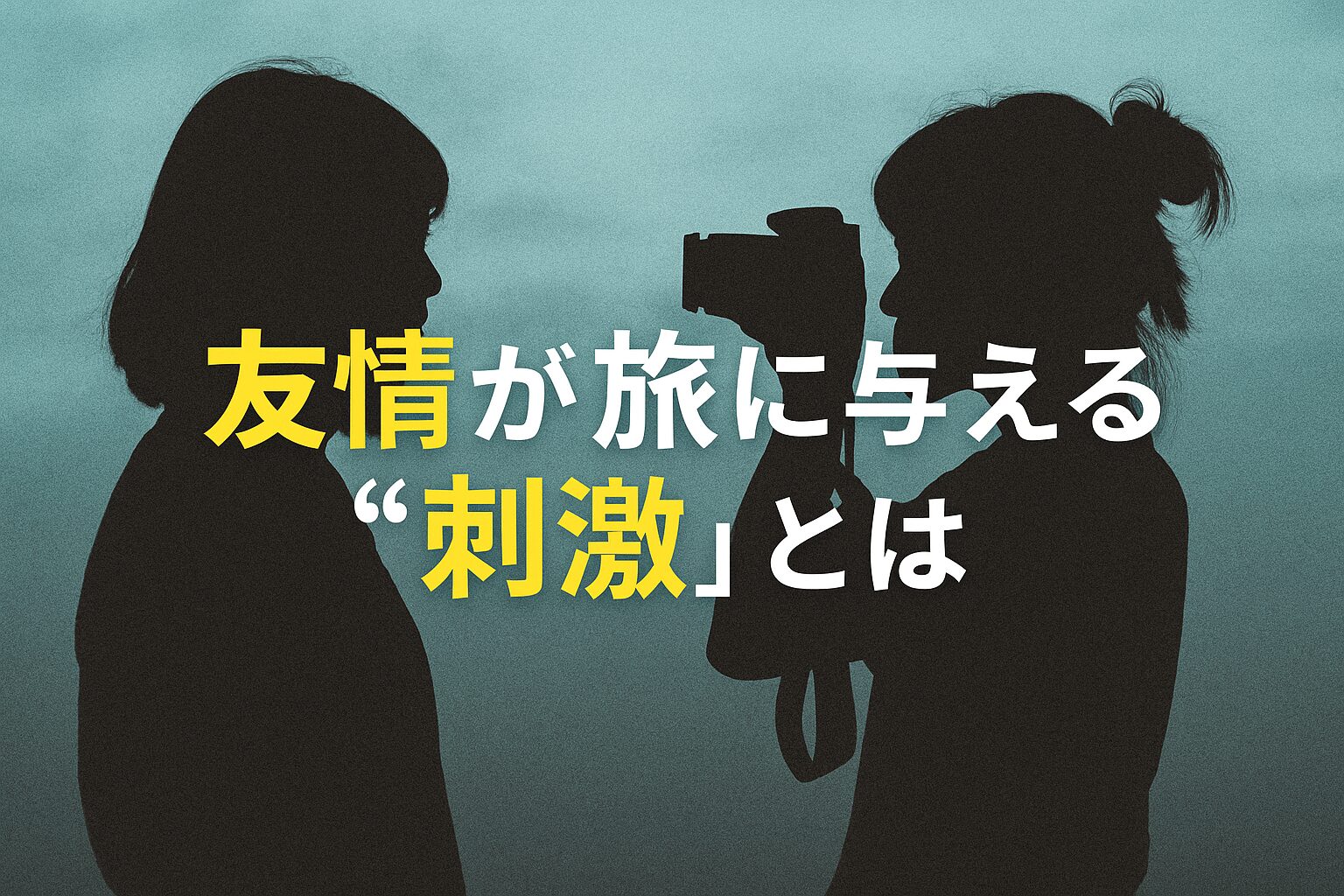


コメント