2025年春クール放送中の『鬼滅の刃』柱稽古編。第3話では、炭治郎の復活とともに、ついに本格的な柱稽古が始まります。
その先陣を切るのは、水柱・富岡義勇。炭治郎との再会と修行を通して、義勇の“過去”と“葛藤”が丁寧に描かれました。
本記事では、第3話のネタバレあらすじを整理しつつ、富岡義勇という人物の核心、そして柱稽古の“意味”について深掘りしていきます。
- 2025年春放送『鬼滅の刃』柱稽古編・第3話の詳細なあらすじ
- 水柱・富岡義勇の内面と「柱ではない」という葛藤の理由
- 炭治郎との対話が義勇の変化に与えた影響
- 柱稽古が意味する物語的・戦力的な重要性
- 今後登場予定の柱たちとの関わりや修行展開の予想
第3話「炭治郎全快‼ 柱稽古大始動」のあらすじ
鬼殺隊本部では柱稽古がついに始動し、炭治郎も完全回復を果たして参加を表明します。
まずは水柱・富岡義勇のもとで修行が始まり、彼の内面と過去が浮き彫りになります。
炭治郎の回復と“新たな戦い”への意志
第3話では、重傷から立ち直った炭治郎がついに完全回復を果たし、再び鬼殺隊の前線に立つ準備を整えます。
本部へと戻った彼は、周囲の隊士たちが柱稽古へ向けて真剣に取り組む姿に触発され、自身も稽古への参加を即決します。
義勇を筆頭に始まる柱稽古の存在は、鬼との決戦を前に全体の戦力底上げを図る重要な施策とされています。
炭治郎は自分に課せられた使命を再確認し、修行によってさらなる強さを身につけることを自らに誓います。
彼の強い意志は、稽古を受ける姿勢だけでなく、柱たちとの関係構築においても大きな意味を持ち始めています。
柱稽古の初戦は富岡義勇からスタート
柱稽古の最初の相手として登場したのは水柱・富岡義勇で、彼の修行場は道場のような静かな空間でした。
しかし義勇は一切剣を抜かず、黙ったままの稽古を続けており、参加した隊士たちは戸惑いと緊張の空気に包まれます。
その独特な態度は、他の柱たちとの大きな温度差を感じさせ、義勇が稽古に本気で向き合っていないようにも見えました。
表情に乏しく、言葉少なな彼の振る舞いは、稽古の場においても“壁”を作っているように映ります。
ただ一人炭治郎だけが、義勇の沈黙の裏に隠された本心を感じ取り、彼に近づこうと努力を重ねていきます。
富岡義勇の葛藤と変化|過去との対峙
表向きは静かに見える義勇ですが、その内側には強い後悔と劣等感が存在していました。炭治郎との関わりの中で、その本音が徐々に明かされていきます。
なぜ義勇は「自分は柱ではない」と言い続けるのか
義勇が「自分は柱ではない」と語る理由は、過去の最終選別での出来事に深く起因していることが明かされます。
本来生き残るはずだった同期が命を落としたことで、義勇だけが柱として称されることに強い罪悪感を抱えていました。
この過去の経験が、義勇にとって“自分は実力で選ばれた存在ではない”という自己否定につながっています。
そのため、彼は柱という肩書きにふさわしくないと感じ続け、他者との距離を意識的に保ち続けてきました。
義勇の口から明かされるこの苦悩は、炭治郎をはじめとする他者にとっても、彼の孤独の理解につながる重要な一歩となります。
炭治郎との対話が引き出した“義勇の本音”
炭治郎は義勇に対して一貫して尊敬の意を示し、自分の成長のために彼から学びたいという真摯な思いを伝えます。
その率直で温かな言葉は、義勇の心の奥にある“誰かの力になりたい”という抑えていた感情を揺り動かしていきます。
口数の少ない義勇も、炭治郎との静かな対話の中で少しずつ自身の心境を言葉にするようになっていきました。
過去に囚われた義勇がようやく一歩を踏み出し、自分自身の過ちや恐れと向き合う姿が丁寧に描かれています。
そしてこの対話こそが、義勇が再び「柱として教える」立場に戻るためのきっかけとなった重要な瞬間です。
修行と心の成長|演出と精神描写の妙
剣技を通じて描かれる柱の哲学、そして炭治郎の内面的成長が見どころです。戦闘だけではない“学び”が柱稽古編の軸となっています。
義勇の剣技に込められた「水の呼吸」の美しさ
富岡義勇の「水の呼吸」は、まるで流れる水のようにしなやかでありながらも鋭さを秘めた剣技で構成されています。
アニメ第3話ではその動き一つひとつが丁寧に描写されており、作画と演出の両面からも非常に高く評価されています。
水の刃が空間を滑るように展開される演出は、見る者に静けさと緊張感を同時に与える映像美を生み出しています。
炭治郎はその美しい剣技に目を奪われながらも、義勇の中にある強い信念と覚悟を感じ取っていきます。
“静けさ”を極めた呼吸が、彼の内面の葛藤や優しさを体現しており、キャラと技が見事に一致しています。
炭治郎の精神力と成長の兆しに注目
義勇の無言の稽古に対しても、炭治郎は真摯に向き合い、常に前向きな姿勢で努力を重ね続けています。
自分の未熟さを受け入れつつ、彼は稽古の中から技術だけでなく“人としての成長”をも得ようとしていました。
修行中の表情や動きにも、以前とは異なる落ち着きや力強さが見られ、視覚的な成長の描写も印象的です。
義勇の剣を“見るだけ”でも多くを学び取ろうとする炭治郎の集中力は、以前よりも格段に高まっています。
精神面・感性・気配の読み取り力といった要素で、炭治郎の“柱への歩み”が着実に進んでいると感じさせる描写でした。
柱稽古が意味するものとは?
単なる鍛錬の場ではなく、戦いに向けた「精神的継承」の意味も大きいのが柱稽古の真価です。柱たちが自らの技術と信念を後進に伝える過程が、物語の厚みと緊張感を高めていきます。
鬼殺隊士たちの底上げがなぜ必要なのか
柱稽古は、上弦の鬼たちとの決戦に向けて、全隊士の戦闘能力と精神力を高めることを目的とした特別な修行です。
これまでの戦いで鬼殺隊の損耗は激しく、限られた時間の中で戦力強化が急務と判断されました。
特に“柱”クラスの強さと経験を持つ者からの直接指導は、若手隊士にとって非常に貴重な機会です。
鬼の上弦との戦闘は、柱以外では太刀打ちできないほどの実力差があるため、組織全体の底上げが必須とされています。
柱稽古によって、「戦える者」と「支える者」の役割も明確になり、部隊の結束力を強める狙いも込められています。
柱たちの内面描写から見える“決戦前夜”の緊張
柱稽古では、技術的な鍛錬と同時に、それぞれの柱たちが抱える“心の葛藤”も描かれる構成が特徴です。
第3話の義勇に続き、今後登場する柱たちもそれぞれ過去や決意、覚悟を稽古という形で隊士たちに伝えていきます。
彼らはただ強いだけでなく、失ったものや背負うものを抱えながら戦っているという側面が印象的に描かれます。
物語は“稽古”という静かな時間の中で、戦闘以上に濃密な感情とドラマを描き出しているのが柱稽古編の特徴です。
それゆえ、戦いの前の“静寂”としての稽古が、決戦の行方を左右する重要な局面であることが伝わってきます。
次回予告と今後の展開予想
炭治郎が次に向かう柱のもとで、さらなる精神と技の成長が描かれていくことが期待されます。登場が予告されている柱たちも含めて、物語は一気に加速する局面に差し掛かろうとしています。
伊黒小芭内、時透無一郎らの登場はいつ?
次回以降、蛇柱・伊黒小芭内や霞柱・時透無一郎といった他の柱たちが順番に登場してくると予告されています。
それぞれの柱は、独自の価値観と戦闘スタイルを持ち、炭治郎や隊士たちとどのような関係性を築くかが注目されています。
特に伊黒は無口で厳しいタイプであり、どのように稽古を進めるかは、義勇とはまた違った緊張感が予想されます。
無一郎はすでに上弦を討伐した実績を持つ実力者であり、彼の戦闘哲学や精神面にもスポットが当たる可能性があります。
それぞれの柱が登場することで、物語がより重層的になり、隊士たちの修行もさらに熾烈なものへと移行していきます。
それぞれの“覚悟”が交錯する物語へ
柱稽古編は、戦いそのものというよりも、「戦いに臨む前の心構えと準備」がテーマとなったエピソード群です。
それぞれの柱が背負っている背景や、鬼に対する覚悟、守りたいものへの想いが少しずつ描かれていきます。
炭治郎はそれらの覚悟を受け取りながら、自身の成長と向き合い、真の意味で“柱に匹敵する存在”を目指していきます。
また、柱たちにとっても炭治郎との交流が、彼らの過去や信念を再確認する時間として機能しています。
物語は静かに、しかし確実に“最終決戦”という重たい局面へと向かっており、その緊張感がひしひしと伝わってきます。
まとめ|義勇の沈黙の裏にあった“優しさ”と“責任”
義勇が抱える葛藤と炭治郎のまっすぐな姿勢が交差した第3話は、心の奥に響く“静かな名場面”が印象的でした。
剣を振らない稽古、語られない本音、その一つひとつが、柱稽古の意味をじわじわと視聴者に伝えてきます。
次なる柱との出会いによって、炭治郎がどのように変わっていくのかにも注目が集まります。
柱稽古編はここから本格的な加速へと入り、鬼との決戦に向けた土台が静かに築かれていく重要な時間です。
富岡義勇の変化と炭治郎の成長は、柱稽古編の核心に位置づけられる大切なドラマと言えるでしょう。
- 第3話では富岡義勇の“沈黙の裏の本心”が丁寧に描かれた
- 義勇は「柱を名乗れない」と語るも、炭治郎の言葉で心に変化が生まれる
- “水の呼吸”の演出美と炭治郎の精神的な成長も見どころ
- 柱稽古は鬼殺隊の底上げと、柱たちの心の継承を描く重要な時間
- 今後の展開では伊黒・無一郎らの登場と“覚悟の交錯”が期待される

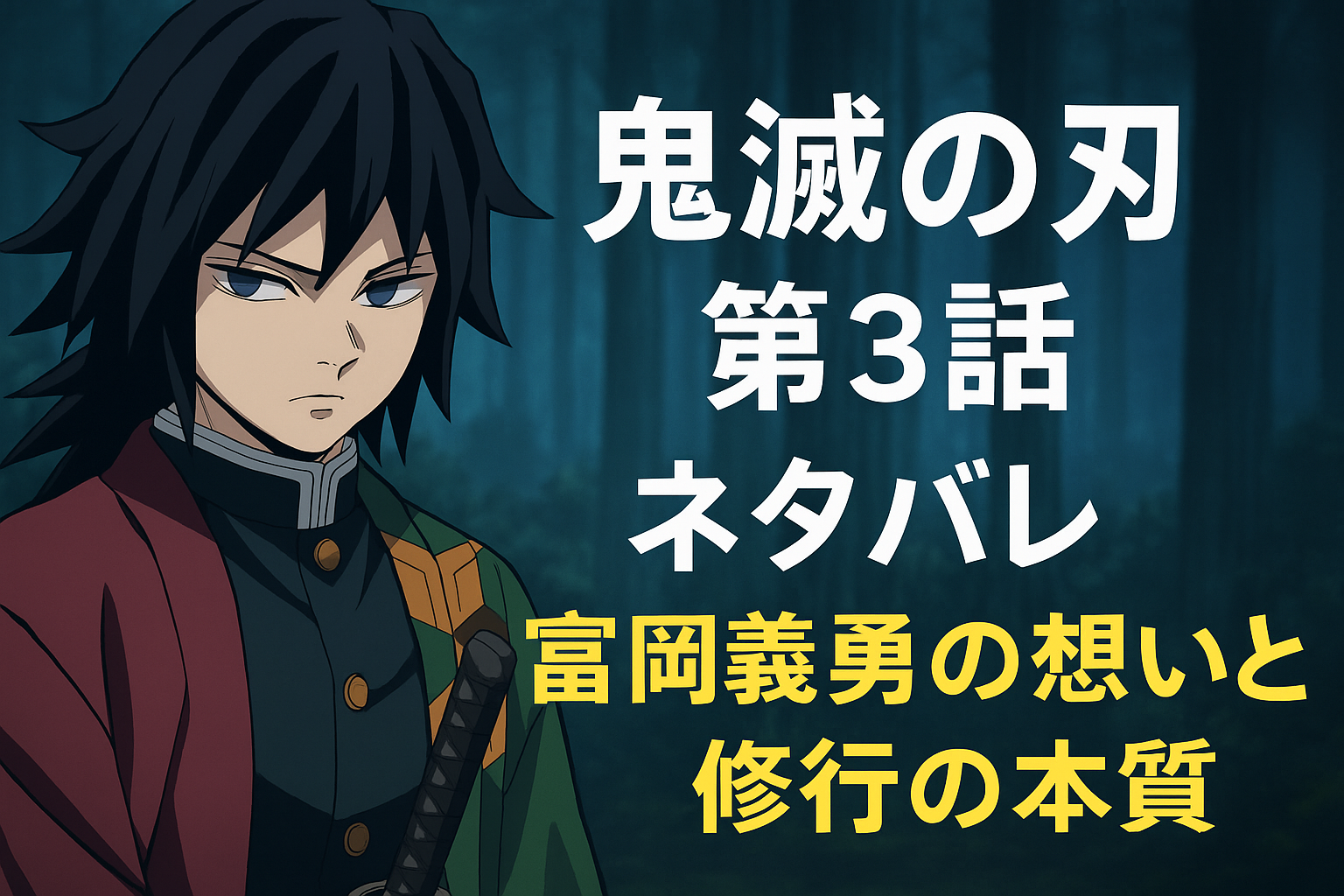
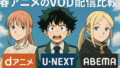
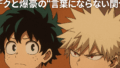
コメント