『よふかしのうた』第2期でもCreepy NutsがOPテーマを担当していることに、ファンの間で注目が集まっています。
1期と同じアーティストが続投することで、作品の世界観や“夜の空気”がどのように変化したのか気になる人も多いのではないでしょうか。
この記事では、Creepy Nuts続投の意図や、1期OPとのテーマの違い、映像演出の変化、そして視聴者の反応から見えてくる感情の動きまで、丁寧に読み解いていきます。
この記事を読むとわかること
- Creepy Nuts続投の背景にある制作陣との信頼関係
- 第1期「堕天」と第2期「Mirage」の世界観と心情描写の違い
- 映像と音楽が生む“湿度のある夜”の演出と受け手の心理反応
なぜCreepy NutsがOPを続投?制作陣との信頼関係が鍵
作品タイトルとリンクする楽曲との絆
「よふかしのうた」と聞いて、まず頭に浮かぶのがCreepy Nuts。これはもう、単なる“主題歌担当”というより、作品と一心同体のような関係です。
そもそも第1期のOP曲「堕天」は、作品タイトルそのものとリンクしており、楽曲がアニメを説明し、アニメが楽曲を広げるという、ちょっと理想的すぎる関係性が成立していました。
そんな中での第2期、OPも当然のようにCreepy Nuts続投。これは制作陣にとって“挑戦”というより“信頼と必然”の選択だったのではないかと思わせられます。
なにしろ、夜の空気、路地裏の孤独、未明の吐息まで音で描けるアーティストって、実はそうそういません。
「よふかしのうた」という作品が放つ夜の哲学と、Creepy Nutsの言葉遊びとリズム感の妙が交わった時点で、これはもう分離不可能な“夜の同盟”です。
続投はむしろ「え?それ以外の選択肢があるの?」というレベルの納得感でした。
「夜」を表現する唯一無二のアーティスト
ラッパーとDJのユニットであるCreepy Nutsは、深夜ラジオ文化や夜の街のリアリティを作品に持ち込む達人です。
彼らの楽曲には「夜を知ってる人の声」が宿っていて、しかもそれが“わざとらしくない”のが強い。これは実際に“夜”という時間帯に何かしらの思い出がある人には、刺さりすぎるくらい刺さるんです。
第1期のOPでは、夜が優しくて居心地のいいものとして描かれていました。一方で、第2期では夜が少しずつ変質している。
孤独はそのままに、どこか粘っこくて、後ろめたい空気が漂ってくるようになっている。そんな“夜の質感の変化”を、Creepy Nutsは楽曲でも自然に描き出しています。
もしも他のアーティストがOPを担当していたら、「うまくやったかもしれないけど、何かが違う」っていう感覚を多くの人が覚えたのではないでしょうか。
彼らでなければ表現できない“よふかしの音”というものが、すでに確立されているんですね。
継続起用がもたらす安定と深化
もちろん、アニメ作品においてOP主題歌が同じアーティストで続くというのは、ある種の“賭け”でもあります。視聴者に「また同じ人か」と思われるリスクもゼロではありません。
しかし「よふかしのうた」においては、むしろ続投によって“進化”を示すことに成功しています。
というのも、第2期OP「Mirage」は、第1期とはまったく違う夜の顔を見せています。「堕天」が夜に逃げる若さの躍動を歌っていたのに対し、「Mirage」は夜にとどまることの苦さや未練を滲ませている。
これによって、単に“同じユニットが歌っている”という事実が、“物語と音楽がともに成長している”という表現へと変化しています。
継続とは守ることではなく、掘り下げること。そして、Creepy Nutsはこの掘り下げを、あくまで等身大の言葉と音で実現しているのです。
変わらぬ声で、変わりゆく夜を歌う。これほどしっくりくる続投、なかなかありません。
1期「堕天」と2期「Mirage」の世界観の違い
1期OPは“夜の優しさ”がテーマ
第1期のOPテーマ「堕天」は、一言でいえば“夜のやさしさ”を詰め込んだような楽曲でした。
逃げ場所としての夜、自分でいられる夜、何も決めなくていい時間の象徴としての夜。歌詞にもサウンドにも、その解放感と寛容さが滲んでいました。
ナズナとコウの関係性も、どこか“夜の遊び”という枠に収まっていて、まだ深刻でも執着でもない、軽やかな距離感が描かれていたのが印象的です。その空気に、Creepy Nutsのスピード感とリズムの妙が絶妙にマッチしていました。
あの頃の夜はまだ甘く、自由で、少し背徳的で、それがとにかく心地よかった。視聴者にとっても「自分の10代の夜」を重ねてしまうような、妙な懐かしさを呼び起こす曲だったのではないでしょうか。
2期OPは“後悔と揺らぎ”を映し出す
対して第2期のOP「Mirage」は、一転して夜の“質感”が変わります。音数は少なめ、テンポもやや抑えめ。
そのぶん、1音1音に余白があり、聴いているこちらも「この隙間に何か大事なことが詰まってる気がする…」と勝手に深読みしてしまうような作りです。
歌詞にも、確信のような言葉は少なく、どこか含みや回避が多い印象。それが逆に、夜の中で考えすぎてしまう人間のリアルな内面を表しています。
1期が「夜っていいな~」なら、2期は「夜って……うん、まあ、そうだよな」と一拍おいて共感する感覚でしょうか。
明確なメッセージよりも、余韻と揺らぎを楽しむタイプの曲。それだけに、聴き手の解釈に委ねられる部分が多く、聴くたびに違う印象を受けるという声も多く見られました。夜って、そんなもんですよね。
歌詞ににじむ大人の未練と影
1期が10代の夜なら、2期の「Mirage」は20代〜30代の夜かもしれません。あの頃みたいに何かに飛び込む衝動は薄れ、代わりに「選べなかったもの」や「戻れない時間」がじんわりと胸に残るようになってくる。そんな“大人の夜”を見事に歌っているのがこの曲です。
歌詞に登場するフレーズは、一見なんてことない言葉にもかかわらず、文脈や曲の流れで突然ずしっと心にくる。たとえば「未練が形になったような」という表現なんて、夜の街でふと立ち止まってしまうような感覚を呼び起こします。
この“ぼんやりした切なさ”は、ただの暗さではありません。光を求めて動いた人間だけが感じる影。
Creepy Nutsの言葉選びが見事にそれを表現していて、「大人ってつらいけど、こういう夜を知ってるのも悪くないな」と思わせてくれます。
映像演出にも変化!色彩とカットで見せる進化
1期よりも湿度の高い演出へ
第2期のOP映像を見てまず感じるのは、「湿度、上がってません?」という印象です。1期の映像がどこか涼しげで乾いた夜風のようだったのに対し、2期はもっと粘り気がある。
まるで雨上がりのアスファルトが蒸発していくような、そんな肌にまとわりつく空気感が漂っています。
色彩も変わっています。1期はネオンのピンクやブルーがパキッと映えていたのに対して、2期ではより落ち着いた、くすみのあるグラデーションが多用されています。
暗がりの中に差し込む黄色や紫の光が、どことなく不安定な心理状態を反映しているかのようです。
これは意図的に「夜の印象」を変えている演出でしょう。ただ楽しい夜、自由な夜、というフェーズを抜けて、もっと複雑で濃厚な“感情が沈む夜”へとシフトしている。その映像表現が視覚的にも見事にアップデートされているわけです。
ノンクレジットOPでの情緒表現
第2期のOPはノンクレジット版が先行公開され、その完成度の高さにSNSでも驚きと絶賛の声が相次ぎました。映像が楽曲とぴったりリンクしているだけでなく、ひとつひとつのカットに意味を感じさせる作りになっているのが特徴です。
たとえばコウが立ち尽くすシーン。彼の表情は大きく動きませんが、その周囲の景色の揺れや色の変化が、彼の迷いや葛藤を物語っています。
セリフも字幕もないのに、心の声が聞こえるような感覚。これは“映像で感情を語る”という演出の理想形のひとつでしょう。
ナズナの登場カットもまた象徴的で、彼女がまるで“視線そのもの”のように描かれています。
正面から見つめられるのではなく、こちらが誰かを覗いているような構図が多く、見る側にも“夜の覗き見感”を味わわせてくれます。ちょっと背徳的、でもクセになるやつです。
映像と音楽が共鳴する設計
OPの映像と音楽がここまで自然に共鳴している作品は、実はかなり珍しいです。よくあるのは、楽曲が格好良いけど映像が追いついてないパターン、もしくは逆のケース。
しかし『よふかしのうた』の第2期OPは、曲のリズム、抑揚、ブレイクに合わせてカットが切り替わり、まるで一本のミュージックビデオを見ているような完成度です。
しかも、その“MV感”がただのオシャレ演出で終わっていない。1期との違いやキャラの感情、物語の背景を視覚的に掘り下げる手段として機能しています。
映像のテンポがゆるやかになった分、余白が増えて、受け手が“考える余地”を持てるようになったのも大きな変化です。
要するに、見るたびに何かを見落としていたことに気づくタイプのOPです。1回じゃ足りない。2回目以降に見えてくる細部にこそ、制作者たちの本気と、Creepy Nutsの音楽との深い対話が詰まっているのです。
ファンが感じた違和感と共感、“夜の心理描写”の変化
変化に驚く声と納得する声
第2期OP「Mirage」が初めて公開されたとき、ファンの間ではちょっとしたざわつきが起きました。
「え? これCreepy Nuts?」という声や、「前よりダークじゃない?」と驚くリアクションも少なくありませんでした。
ですが、その第一印象は、数日後には「やっぱこの空気感、クセになる…」という妙な納得感へと変わっていきます。
これはまさに“違和感からの共感”の典型です。あえて前作とトーンをずらし、リスナーの感情をゆさぶってくる構成は、まるで夜中に突然くるメッセージのよう。
受け取り方によっては不安にもワクワクにもなる。そんな微妙な“心の振り子”が、ファンの中でも静かに動いていたようです。
SNSでも「最初は違うかもって思ったけど、今はもう耳に馴染みすぎてる」といった声が多く見られ、「違いを楽しむ」余裕があるのがこの作品のファン層の特徴かもしれません。
考察班にとっても、こうした変化はネタの宝庫ですね。
「ただれた感情」に惹かれる視聴者の心情
「Mirage」の歌詞や雰囲気には、どこかくたびれたような、あるいは諦めに近い感情が漂っています。
それを「ただれた」と表現した視聴者も多く、意外にもこのネガティブな響きが、強く共感を呼んでいるのです。なぜかというと、たぶん“夜”にしか現れない感情って、まさにそういうものだからです。
仕事や学校が終わって、すべての役割を脱いだ後にだけ現れる素の気持ち。誰にも見せない未練や後悔、やり過ごした感情。
そうした「処理しきれない心の残りカス」を、Creepy Nutsは音と言葉にしてくれた。それがファンの深層心理にスッと入り込んだわけですね。
「優しすぎない夜」が描かれているからこそ、それでも夜を好きでいたいと思う気持ちが浮き彫りになります。そんな矛盾ごと肯定するような曲調に、静かに支えられている人も多いのではないでしょうか。
音楽と映像から受ける“心のざわつき”
OP映像と音楽の組み合わせは、視聴者に明確な答えを与えるというより、むしろ「問い」を残していきます。
何を見たのか、なぜ心がざわついたのか、自分で言語化しないと消化できないタイプの感覚です。これはある意味、すごく贅沢な体験だと思います。
「よふかしのうた」という作品自体が、元々“感情の行き場”を描く物語なので、OPで感じたざわつきがそのまま本編への導入になっている感覚もあります。
視聴者の中には、「OPを見終えた時点で、もう1話分見た気になる」という人もいました。これは褒め言葉だと思っていいでしょう。
“感情がはっきりしない”ことに不安を覚える人もいますが、そのあいまいさを丁寧に味わえるのがこの作品の良さ。
だからこそ、ただの主題歌以上に「Mirage」が担っている役割は大きく、ファンの記憶にも深く刻まれていくのです。
まとめ:Creepy NutsのOP続投が導いた“夜の深化”
第2期でもCreepy NutsがOPを担当するという選択は、作品の世界観を守りつつ、新たな夜の表情を引き出す鍵になっていました。
1期の「堕天」が描いた自由で軽やかな夜に対し、「Mirage」は未練や迷いを帯びた湿った夜を描き出しています。
映像もまた楽曲と連動し、より感情の深部に踏み込んだカットや色彩表現が印象を強めています。
視聴者の間でも、最初の違和感から徐々に共感へと変わるプロセスが語られ、感情を“預けたくなる”ようなOPとして受け止められていました。
ただ格好いいだけではない、心のざわつきや静かな興奮を生むOP。それを“当然のように”続投できることこそ、Creepy Nutsとこの作品の関係の深さを物語っているのではないでしょうか。
この記事のまとめ
- Creepy Nutsが続投する理由は作品との深い相性
- 1期と2期でOP曲の“夜の表情”が大きく変化
- 映像演出もより湿度と余白を感じる構成に進化
- 「Mirage」は聴く人の内面を静かに揺らす楽曲
- 視聴者の間では違和感から共感へと感情が変化
- 音楽と映像の“ざわつき”が作品の深みを生んでいる



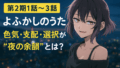
コメント